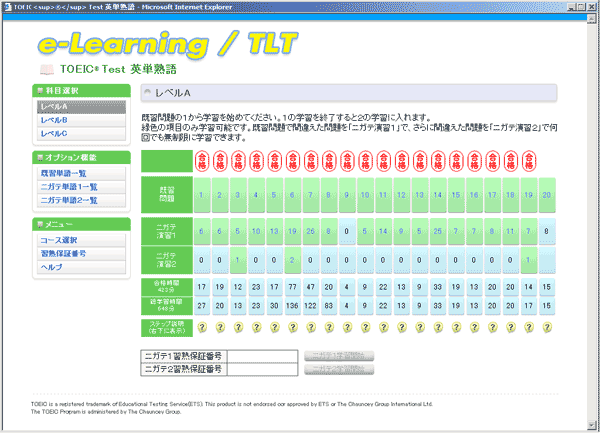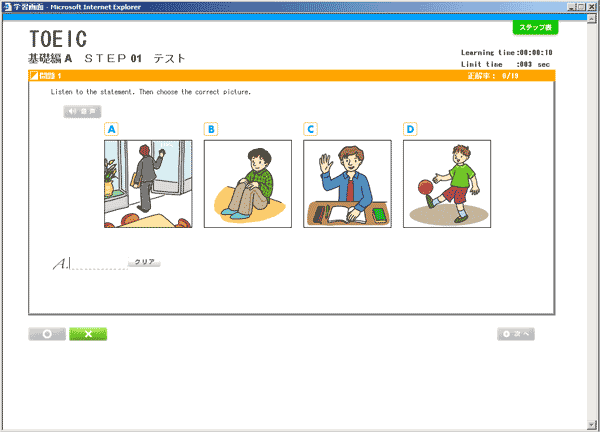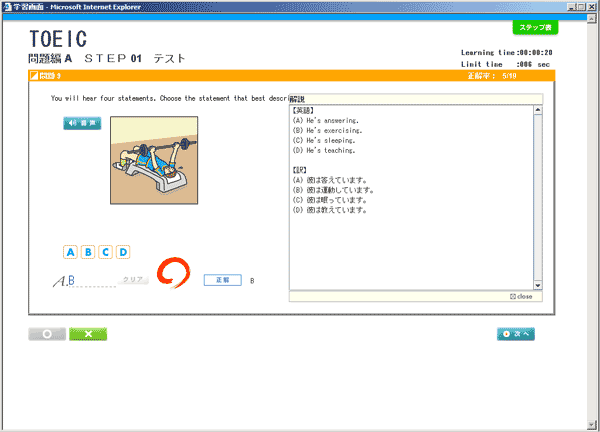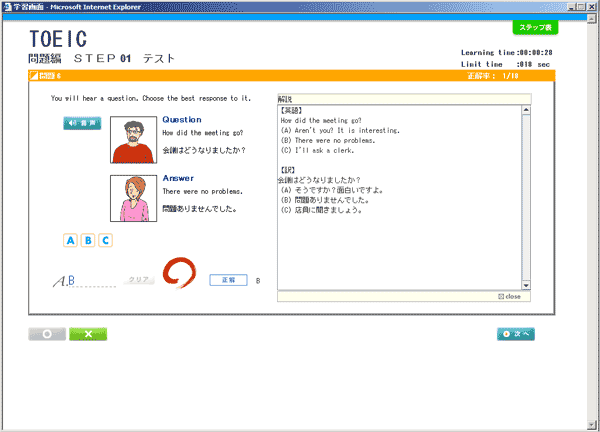TOEIC TEST対策Aコース
TOEIC(R) TESTについて
TOEIC(R) TESTの概要は以下のとおりです。
より詳しい情報、検定受験お申し込みについては、
TOEIC(R)公式ホームページ
をご覧下さい。
スコアについて
- リスニングスコア5点~495点+リーディングスコア5点~495点
トータル10点~990点(5点刻み)
TOEIC(R) TESTスコアと能力レベル
- Aレベル:860点~…Non-Nativeとして十分なコミュニケーションができる
自己の経験の範囲内では、専門外の分野の話題に対しても十分な理解とふさわしい表現ができる。
Native Speakerの域には一歩隔たりがあるとはいえ、語彙・文法・構文のいずれをも正確に把握し、流暢に駆使する力を持っている。 - Bレベル:730~860点…どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えている。
通常会話は完全に理解でき、応答もはやい。話題が特定分野にわたっても、対応できる力を持っている。業務上も大きな支障はない。
正確さと流暢さに個人差があり、文法・構文上の誤りが見受けられる場合もあるが、意思疎通を妨げるほどではない。 - Cレベル:470~730点…日常生活のニーズを充足し、限定された範囲内では業務上のコミュニケーションができる。
通常会話であれば、要点を理解し、応答にも支障はない。複雑な場面における的確な応対や意思疎通になると、巧拙の差が見られる。
基本的な文法・構文は身についており、表現力の不足はあっても、ともかく自己の意思を伝える語彙を備えている。 - Dレベル:220~470点…通常会話で最低限のコミュニケーションができる。
ゆっくり話してもらうか、繰り返しや言い換えをしてもらえば、簡単な英語は理解できる。身近な話題であれば応答も可能である。
語彙・文法・構文ともに不十分なところは多いが、相手がNon-Nativeに特別な配慮をしてくれる場合には、意思疎通をはかることができる。 - Eレベル:~220点…コミュニケーションができるまでに至っていない。
単純な会話をゆっくり話してもらっても、部分的にしか理解できない。断片的に単語を並べる程度で、実質的な意思疎通の役には立たない。
受験資格
- 誰でも受けられ、回数制限等もありません
試験日
- TOEIC? TESTの公開テストは年8回(1・3・5・6・7・9・10・11月)全国78都市で実施されます。受験地ごとに実施回数が異なります。
受験料
- 6,615円(税込み)
受験者数の推移
過去10回分を表示しています。
| 回数 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試験月 | 07.1 | 06.11 | 06.10 | 06.9 | 06.7 | 06.6 | 06.5 | 06.3 | 06.1 | 05.11 |
| 受験者数 | 94,274 | 73,720 | 38,328 | 82,453 | 48,591 | 35,706 | 88,613 | 120,064 | 101,223 | 79,432 |
| 平均点 | 567.7 | 569.9 | 582.2 | 562.3 | 567.9 | 569.0 | 572.8 | 562.5 | 545.8 | 565.2 |
※122回(2006年5月)より、新テストに変更
| 教材タイプ | e-Learning(インターネット環境が必要です) |
|---|---|
| 受講期間 | 6ヶ月 |
| 点数保証 | 点数保証あり |
| 費用 | 31,200円 |
| TOEIC(R)対策入門基礎コース | |
|---|---|
| 教材タイプ | TOEIC BRIDGE対応 e-Learning版 |
| 受講期間 | 2012年12月31日まで |
| 点数保証 | 点数保証なし |
| 費用 | 19,500円 |
TOEIC問題例
教科書だけでは学べない、新しい英語力を養います
一生ものの英語力としてTOEICの需要が高まる中、TOEICのスコアアップを目指す人が学習しやすいよう、英語力を向上させるために開発された教材がTOEIC TEST Aコース。頭で考える「英語の勉強」ではなく、瞬発力を養う「英語のトレーニング」をサポートする教材なので、TOEIC対策として最適です。
「英語は英語のまま理解する」という発想
TOEIC TEST Aコースは、大学入試のような英語ではなく、TOEICによる「使える」英語力を徹底的に養う教材です。簡単な英文を繰り返し聞き、日常で使う単語・英文を完全にマスターすることで、英語を英語のまま理解する力がつき、英語コミュニケーション能力は格段に向上します。いわば、直感的に英語を理解する力を身につけることができる教材です。
これからの英語力の指標、そして目標となるTOEIC
TOEICが広く利用されているのは、結果が合否ではなく、点数で示され、英語力をより具体的に評価できる点にあります。その評価基準は常に一定で、受験者は現在の英語能力を正確に把握し、目標スコアを明確に設定することができます。TOEICは、さまざまなレベルの受験者の英語力を客観的に位置づけることができる英語学習の指標です。
TOEIC TEST Aコースは、TOEIC Bridgeにも対応しています
TOEICには、通常のTOEICテストのほかにもうひとつ、TOEICテストへの架け橋として開発されたTOEIC Bridgeがあります。TOEIC TEST Aコースは、どちらにも対応しているので、どんなレベルの受講者にとっても最適な教材です。
安心の合格・点数保証制度
有効期間内にTLTソフトの全学習を終了し、全学習項目に「習熟保証番号」を表示させて下さい。試験の前日までに、「習熟保証番号」と「本試験受験票のコピー」などの必要書類をNewton社にご提出いただきます。公開テストを2回連続受験して、万が一、規定の点数未満だった場合、お支払になった受講料金を全額返還いたします。ニュートンのTLTソフトは、保証番号が表示されるまで学習されれば、必ず目標点数を達成できる完全習熟ソフトだからです。
- 対象テスト…学校・企業など各種団体で開催されるIPテストに付きましては、点数保証制度の対象外となります。ご了承下さい。
- 2回連続の意味…試験に不慣れなために、リスニング等で思うように実力を発揮できないことがあるからです。 また、保証点数に最低点を設けているのは、原理的にそれ以下の実力ではTLTソフトの全学習項目に合格番号を表示させることが不可能と考えられるからです。
- 合格保証制度の趣旨…TLTソフトでしっかり最後まで学習されれば、必ず合格できると私たちは確信していますので、受験者がTLTソフトのシステム通り学習を実行したにもかかわらず、試験において合格を果たせなかったことに対する補償として「全額返還」をするものです。したがって、TLTソフトでの学習を途中で破棄したり、本試験に欠席した方に一切の補償をするものではありません。
保証内容
契約満了より6ヶ月以内にTOEICまたはTOEIC Bridgeの公開テストを2回受験し、2回連続スコアが下記の場合なら返金
- TOEIC TEST…350点以上450点未満
- TOEIC Bridge…100点以上150点未満
提出資料
- 本試験前日までに合格番号をホームページから送信
ブラウザ版(ユーザーIDがW16で始まる方):習熟保証番号送信フォーム
Windows版(ユーザーIDが015で始まる方):合格保証番号送信フォーム - 1・2回目の本試験受験票コピー(それぞれ試験前日必着)
- 1・2回目の公式認定証(試験後に提出)
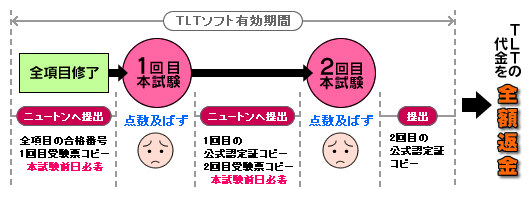
動作環境
eラーニング版
| OS | 日本語版Windows®XP、Vistaが動作するPC/AT互換(DOS/V)機 日本語版Apple Mac OS X 10.4が動作するMacintosh |
|---|---|
| ブラウザ | 日本語版Microsoft Internet Explorer 6.0以降、 日本語版Apple Safari 1.2以降 |
| CPU | Intel Pentium(または同等の)プロセッサ1GHz以上 |
| メモリ | 512MB以上(Windows Vistaは1GB以上) |
| ハードディスク | 空き容量2GB以上必要 |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、256色以上の表示が可能な機種(65536色以上推奨) |
| インターネット | インターネットに接続できる環境が必要(ADSL・光回線などのブロードバンド環境推奨) ■ 常時接続環境→LAN(10/100BASE対応) ■ ダイヤルアップ→モデム(56Kbps以上を推奨) ■ 学習プログラム・学習教材のダウンロード時、学習履歴の送受信時に接続を行う。 ※ダイヤルアップ接続はサポートしますが、通信速度の関係でデータの送受信に時間がかかります。 |
| サウンド | サウンドカード、スピーカー(あるいは、ヘッドホンまたはイヤホン)など音声を再生できる装置が必要です。 |
| ソフトウェア | Java Runtime Edition1.4.2以上 (http://www.java.com/ja/からダウンロードできます) |
※ Windows®は米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※ Pentium®はIntel Corporationの商標または登録商標です。
※ その他の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。